パンノキの生態
原産地と生態
パンノキの原産地は南太平洋に位置するポリネシアです。気候としては亜熱帯または熱帯に属しますので耐寒性はありません。
日本では本州以北では主に植物園で見ることができるほか、数は多くないですが鉢物も流通しています。沖縄には地植えされていたりします。

東南植物楽園近くに生えていたパンノキ
10メートルを超えて旺盛に生育し、10センチから30センチにもなる実をつけ、焼いたり揚げたりして食されます。温度、土壌などの環境が整っていれば、成熟した木には年間200個以上の実が実ります。

熱帯ドリームセンターのパンノキの実
実には種のある品種とない品種があり、種ありの品種は「タネアリパンノキ」、種なしの品種は「タネナシパンノキ」と呼ばれ区別されています。タネナシパンノキはタネアリパンノキを元に品種改良されました。
1本の樹の葉の根元から細長い棒状の雌花と花穂状の雄花が出ます。
管理人宅では鉢植えで育てています。樹高130センチの現在では花は咲いていません。
花の様子はこちらのブログを参照させていただきます。
生育サイクル
- 春 成長、開花、結実
- 夏 成長、果実収穫
- 秋 成長
- 冬 ほぼ休眠
四季がはっきりと分かれる日本においては春に花を咲かせ結実し、暖かい季節に成長、冬季は休眠します。
※熱帯地域ではこの限りではありません。
枝葉の観察
我が家で育てているパンノキを観察してみます。
枝分かれをする木ですが、幼木の頃は一本で成長するようです。先端に切れ込みの入った特徴的な葉が茂っています。

葉は大きいものでは30センチほどにもなります。木の全長に対して随分大きな葉です。
大きくなると葉の大きさは60センチにもなります。
葉の表面には細かな毛が生えており、触るとじょりじょりします。

葉は開く前は鞘のようなものに丸まって入っています。鞘を破って出てきて、大きく広がります。
新しい葉は黄緑色をしており、出た直後でも切れ込みがしっかりと入っています。

葉の出方などを見ると、同じクワ科のウンベラータに似た印象を受けます。
パンノキの基礎知識
基本情報
科:クワ科(Moraceae) 属:パンノキ属(Artocarpus)
世界最大の実をつけるパラミツ(ジャックフルーツ)も、パンノキ属に属します。
種のある品種である「タネアリパンノキ(Artocarpus camansi)」がポリネシアはじめ南太平洋の島々にもちこまれ、品種改良されて「タネナシパンノキ(Artocarpus altilis)」がうまれました、
分類:高木/常緑性
熱帯に生える常緑の高木で、大きくなると高さ20メートルを超えて大きく成長します。
歴史
パンノキの原種は「タネアリパンノキ(Artocarpus camansi)」で、これはニューギニアおよびマルク諸島、フィリピンに固有の種です。
3,000年前、オーストロネシア人(台湾、東南アジア島嶼部、太平洋の島々にまたがって航海術に長けていたといわれる。)によって、もともとこの種が生息しなかったポリネシアはじめ南太平洋へ持ち込まれました。
その後、古代ポリネシア人によりハワイへ持ち込まれたようです。古代ポリネシア人によりハワイに持ち込まれ、根付いた植物をカヌープランツと呼びます。
豆知識
ハワイでおなじみのパンノキ
ハワイではおなじみらしいパンノキ、有用植物としてポリネシア人によって持ち込まれたそうです。
現地では「ウル」と呼ばれています。「ウル」は豊穣と裕福の象徴とされており、葉がハワイアンキルトのデザインとしてよく用いられています。
パンノキは生活の中でさまざまに活用されています。幹からはサーフボードやフラのドラムなどが作られました。
樹液は 糊として、イプヘケのひょうたんのつなぎ合わせやカヌーの板の継ぎ目を埋めるのに使わ れました。葉も、木製のボウルやククイナッツの艶出しに使われたそうです。
バウンティ号の反乱
18世紀末にイギリス海軍の武装船バウンティで起きた艦長に対する反乱事件、いわゆる「バウンティ号の反乱」において、運ばれていたのがパンノキです。
1788年、ウイリアム・ブライ船長率いるバウンティ号は、タヒチからカリブ海にパンの木を運んでいました。
というのも、パンの実が栄養豊富だったため、これを持ち帰り、黒人奴隷の食料とするためです。
しかし、パンノキの輸送を重視し乗組員の住環境をおろそかにした結果、船内で反乱が起き、ブライ艦長以下19人は救命艇に乗せられて追放されてしまいました。
ブライ船長 はその後1792年に再度チャレンジし、1200本のパンの木を無事にタヒチからジャマイカまで移植することができたといいます。
パンノキの育て方
パンノキには育て方のメモが同封されていましたのでそれをもとに育て方を記しておきます。
冬は屋内に入れ、室内でも明るい場所に置いて水を切らさないことがポイント。
| 日当たり | 日当たりでよく育つ。夏の直射を避ける。屋内の明るい場所でも可。 |
| 置き場所 | 屋外、屋内管理どちらも可。冬は屋内へ。 |
| 用土 | 水はけのよいもの(赤玉7:腐葉土3やベラボン等) |
| 水やり | 土の表面が乾いたらたっぷり。葉水も。冬は乾かし気味に。 |
| 温度 | 生育温度は20~30℃。寒さに弱いので冬は8℃以上が無難。 |
| 肥料 | 5~10月の暖かい時期に与える。 |
| 病害虫 | ハダニ、カイガラムシ、根腐れ、低温に注意。 |
| 殖やし方 | 実生、または春から秋の暖かい時期に根伏せ。取り木は不明。 |
栽培環境
原生地では日よけのために植えられるくらいなので日光を好む植物です。
20℃を超えたあたりから生育期に入りますのでできれば屋外で管理します。
屋外に出す際には突然日差しに出すのではなく、徐々に日差しの当たる場所へ移動させ、葉焼けを防ぎます。
日差しには強い植物だとは思うのですが、育てた限りでは強い直射日光に当たりすぎると葉焼けを起こしてしまうことがありますので葉の様子を見ながら置き場所を工夫してください。
耐寒性は弱いので、冬季は室内へ取り込みます。
肥料
5月から10月頃の温かい時期に緩効性の化成肥料を与えます。または、週に1度程度液肥を与えます。
冬季にはは成長が鈍るので肥料は与えないようにします。
病気と害虫
ハダニ:吸汁によって木を弱らせます。薬剤散布によって駆除します。
カイガラムシ:5月頃より暖かくなってくると発生する。分泌物によりすす病を併発することがあるので見つけ次第捕殺する。
用土(鉢植え)
赤玉土、腐葉土、バーミキュライトの配合土に元肥を配合。
植えつけ、 植え替え
冬季を避け、暖かくなった5月から7月頃行います。
枝を出すには
剪定せずに育てていると主幹のみが伸びて枝が出ないことがあります。
主幹の先端を切ってやると、葉の付け根から新芽が出て枝分かれをします。
ふやし方
種まき:種ありの品種の果実の中にある種をまきます。
根伏せ:根をある程度の長さに切って土に埋めておき、先端を少し土の上に出しておきます。
取り木:茎にカッターでぐるりと切れ目を入れ皮と形成層を取り除き、白い部分を露出させます。
1mmくらいは削り取る感じです。
湿らせたミズゴケを取り除いた部分と上下数センチを覆うように巻いて、ビニール等で覆いひもや針金で固定しておくと2,3週間で発根します。(画像は仲間のカシワバゴムの木)
※管理人が実施したところ失敗したので取り木はできないのかもしれません。

パンノキの成長記録
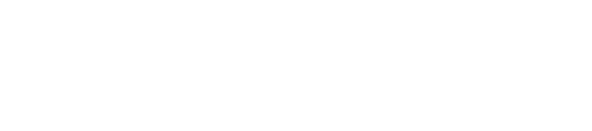





コメント